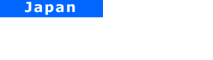21歳になった年のある日、その日の労働を終えて監房に戻って来て見たら、新入班から6人の収監者が私たちの伐木班に配置されてきていた。その中には、拘留場で虚弱1度になって教化所に入所したリュ・ヨンナムという20歳の青年もいた。
20歳とは言ってもまともに食べることができずに育ったためか、丈夫そうには見えず弱々しい体格で、性格も従順だった。事情を聞くと、ヨンナムは3歳年下の妹、ヨンヒと一人になった母親と一緒に暮らしていた。中国に行って米をもらって食べていたという。ヨンナムは中国の農村に行って米をもらって来ていたが、数回国境警備隊の軍人につかまって保安署に連れて行かれたという。最初の数回は若いからと、労働鍛錬隊(北朝鮮の受刑施設の1つで、軽犯罪や経済犯、単純な刑事犯が収監される。該当地域の人民保安省(警察庁)が管理して、強制労働を課して、党と刑法に対する忠誠心を育てる)の刑で終わったが、不法越境の回数が増えたため、「教化3年の刑」を受けて全巨里の教化所に入れられたのだった。
就寝のベルが響くと、監房の一番奥にある私の寝床に横たわって、班長とヨンナムが交わす話に耳を傾けた。私が入所した初日のことが頭に浮かんでヨンナムに同情した。
だがいつものように、新入者たちとは数日間言葉を交わさずに彼らの人柄を見守るつもりだった。伐木班は班長も人情がある人といううわさを聞いて、新入者たちは班長や他の人の質問には謙虚に答えて仲良く生活することを約束した。
翌日、食事の時間になると私は黙って班長のそばに座った。ヨンナムは班長と一緒にご飯を食べる私をちらちらと盗み見ていた。別の新入者たちも若い私が班長と一緒にご飯を食べているのを不思議そうに眺めていた。
当時私は、私たちの作業班の第1組の組長だった。監房の中では班長や組長と、一般の収監者の差は天と地ほどあった。還暦を過ぎた人も、班長とティーの前では敬語を使わなければならなかったし、班長と組長は無条件、敬語を使わなかった。
実際には年が若い私の立場としては、誰に対しても敬語を使わなければ、班長と一緒に教化班を率いて行くことができなかったので、新入者は私をてこずらせた。班長は班長として長い間生活してきたので、初めて見る人の目つきだけで、その人の性格や人柄をある程度把握していた。
私も時間をかけて人を観察する習慣が見についた。性格は善良か、言葉で人をいじめるような習慣があるのか、義理があるのか、利口か、食べ物の前で水火をも辞さない人かということをだいたい把握することができた。
社会のように心を開いた関係を維持することができない教化所では、人の目つきだけを見て内面を把握することができなければ、教化班を導いていく資格がないといえる。ヨンナムのような新入者たちが、地獄のような教化所生活に早く適応できるようにする必要があったが、まずは労働に耐えられるように助けなければならなかった。
教化所は一般の社会とは比べられないほどの重労働に苦しみ、監房に入って来てもきちんと列をそろえて学習して、悪口を言われて殴られなければならない所だ。こうした生活に打ち勝つためには、相当の闘志と忍耐力がなければならなかった。そのため、優先的に彼らの忍耐力を育てなければならなかったし、死に直面していた彼らを1回ずつ起こして立たせてやることが、班長と私がすべきことだった。
私は労働時間以外には新入者たちと話もせず、彼らが何か聞いてきてもまともに答えずに冷たく振舞った。また、監房に先に入って来た人でも後から入って来た人でも、少しでも配慮のない行動を取ったり手を抜いて働いている人には容赦なく、短いが荒々しい雑言を吐いた。
それだけでなく、自分の過ちを他人に被せようとする人たちは年齢にかかわらず、叩いたりぶん殴ったりした。けれども私は、班員の信頼を失わなかった。いくら悪態をついて拳を振り回しても、日曜日ごとにだまってとうもろこし粉のお粥を炊いて班員の飢えたお腹を満たしてやったので、私を無視する人はいなかった。
ヨンナムが私たちの教化班に来てから2ヶ月ほど経ったある日、私は学習しているヨンナムの顔をじっと見た。ぽんと飛び出したほお骨やすっと落ち込んだ目、耳介が目立ちぽこんとへこんだこめかみ、長い耳、細い首に飛び出た咽彦……。
「ヨンナム、虚弱病にかかって死にそうなのか」
突然の問いかけに驚いたヨンナムは、わけも分からず私をじっと見つめた。
「ヨンナム、そんなにしていたら生きて家に行けないよ。食べることを考えるのはやめなさい!」
班長もヨンナムを見て、重々しく言った。
「ヨンナム、こっちに来い!」
声をかけると、ヨンナムは私の前に来て座った。自分は早く動くと言っていたが、虚弱病にかかった体はのろのろと、まだるっこく動いていた。ヨンナムは何も言わずに自分をにらみつける私の目つきに緊張していた。監房の人全員がかたずをのんで私を見つめていた。
「さあ、おまえの席に行きなさい!」
ヨンナムは一層面くらって、席から立ち上がりながら私の機嫌を伺っていた。
「ヨンナム、俺のところに来ようとしていた間は、食べることを考えていなかっただろう」
私はその時、初めて微笑んだ。私が2ヶ月経ってヨンナムに見せた、最初の笑みだった。監房の中の張り詰めていた緊張感がすっと和らいだ。
「誰でも辛い時は家族のことを思いなさい。私たちは1日3食、トウモロコシご飯だけでも食べられるが、外にいる家族は草のお粥を食べながら暮らしているということを忘れないで」
私の短い演説に、皆が死んだ鼠のように静まった。班長も私も、ヨンナムも他の収監者たちも皆、愛する家族に思いを馳せた。
「班長、サ先生が振り向いています!」
感傷的になったのもつかの間、廊下で行ったり来たりしながら、監房でちゃんと学習しているかチェックしている雑夫組長の声を聞いて、皆再び将軍様の教示をつぶやき始めた。翌日、うちの班の労働課題がすべて終わった後、私はヨンナムに近付いた。泣きべそをかきながら斧を振り上げているヨンナムを見たが、本当に仕様が無かった。
細い腕で辛そうに斧を振り下ろしているが、斧の勢いに全身が揺さぶられてふらふらしていた。斧を入れた時に飛び散った木屑がまぶたに当り、涙まで流しながら悪戦苦闘している。ヨンナムはこの班にやってきて2ヶ月過ぎても、1人で木を1本切ることもできずに、担当している管理人の鞭にしょっちゅう打たれていた。
「ヨンナム、ちょっとどけ!」
私は急いで木を切ってばらばらにして、ヨンナムの綱に縛り、木を引っ張りやすいように下の方を整えてやった。呆然とみつめているヨンナムは、とても感謝をしているといった目で私を見ていた。共同生活をしている集団の中には何かあげても憎い人がいるかと思えば、何もあげなくてもやさしい人がいるが、私にはヨンナムが実の弟のような存在のように思えてきた。
ヨンナムが善良で、他人を傷つけることができないきれいな心を持った奴だったからだ。他の人は寒くてお腹がすいていたら、他人は死んでも自分のことだけ考えているが、ヨンナムは自分が苦しい時も他の人に譲ることができて、私がご飯をあげても、必ず他の人と分けて食べていた。それに、うちの班を担当する保安員がヨンナムをこっそり呼びつけて私と班長のことを問い詰めた時も、ヨンナムは打たれながらも口を割らなかった。
私は班長と力を合わせて、虚弱なヨンナムの体をなんとか回復させなければならないと思い、特に関心を持つようになった。 作業に出る日に、ヨンナムには休役(作業に出ずに監房で待機すること)を指示して、ポンポン粉を5キロ手渡した日もあった。
監房ごとに1人か2人は班長の権限で休役を指示することができた。休役者は、本当ならば病房の1号室に衛生員の監視を受けて監禁されることになっていた。だが私はトウモロコシ餅を作って食べられるビニール袋を用意して、水を1杯汲んでおいて、ヨンナムをそのまま監房に残して外から鍵をかけた。
1号衛生員と雑夫組長には、サ先生が点検する時は適当に遮ってほしいと頼み、ヨンナムには「何も心配しないで、食べたい時は食べて、寝たい時は見つからないように監視窓の下にぴたっとくっついて寝るんだぞ!」と言って作業に出た。夕方監房に戻って来たら、私の置いて行ったポンポン粉はあまり減っていなかった。2キロ全部食べただろうと思っていたが、食べた痕跡があまりなかった。
「ヨンナム、どうして食べなかったんだ。具合が悪いのか」
「いいえ。これを1人で食べなさいと言われたら、全部食べる時もあると思いますが、横に誰もいないので1人で食べようとしてもすぐにお腹が一杯になって、あまり食べられませんでした」
残った分は教化班の人と分けて食べると言うのだった。私はヨンナムをじっと見つめて、「お前は必ず生きる!」と言ってやった。他の人は、次の日にまた食べると言うような状況なのに、虚弱1度にかかったヨンナムは、自分の前に差し出されたものを他の人と分けて食べたいと考えたのだ。考えれば考えるほど、ヨンナムに対する情がつのった。
4ヶ月後に、ヨンナムの体重は67キロになった。163cmあるヨンナムは体重が67キロになり、顔や体がむくむくと膨れていた。その膨れた肉が筋肉になればよいのにと思った。私はヨンナムに「もじもじ」というニックネームを付けた。
ある日私が「おい、ヨンナム!」と呼んだが返事がなかったので、「おい、もじもじ!」と呼んだら、堂々と「はい!」と答えてきた。それを聞いた班員みなが大笑いしたので、その日からヨンナムのあだなは「もじもじ」になったのだった。
ある日、ヨンナムを連れて炊事場に食事をしに行った。節日の休日や日曜日には、炊事場の組長リャン・ミョンハクがきまって、私のために食事を用意して待っていてくれた。ただの飯ではなく、人が食べる時に使う器に暖かいご飯を盛って、みそまでのっけてくれて人間らしい食事をさせてくれた。
炊事場に入って行ったヨンナムはしきりにきょろきょろと見て回し、辺りをうかがいながらそわついていた。炊事場は数人の班長や組長以外の人は入ることができない場所だったからだ。
引き出しがついている高圧炊飯器と、その下に大きなふたが2つ向い合って付いているお汁用の鍋(電気が無いため、薪を燃やすボイラーの蒸気を利用する鍋)、ご飯をかき交ぜる板、シャベル、ご飯をつくための壺、水タンク、粉砕機などヨンナムは好奇心にあふれた目であれこれと眺めていた。
「ここに入って来たことがない班長よりもお前の方が上だな!」と言ったら、リャン・ミョンハクが噴き出した。リャン・ミョンハクが席をはずした時、ヨンナムが急にべそをかきながら話し出した。
「班長、どうもありがとうございます」
「おいおい、誰が死んだというのだ」
「以前、新入者だった時に班長が初めて私の木を切り倒してくれて『大変だろう』と聞いてくれた時、どれだけ力になったか……。最初は班長があまり話さなかったので、怖くてきつい人ではないかと思ったんです。そして私が虚弱病にかかった時、『お前は必ず生きる!』と言ってくれた時、本当に信じられました。班長がいなかったら僕は多分…」
「もういい、こいつ! 男が泣くとは」
ヨンナムの後に、弟分の新入者が6人くらい入って来たが、私はヨンナムほど関心をもってやることができなかった。どこでも連れて行った所では機転をきかせて守ってやり、誰にでもかわいがられていたヨンナムを私はいつも横に置いていた。
だが、私とヨンナムの縁はあまり長く続かなかった。私は虚弱病にかかって生死の境から生き返った彼が、私のそばを離れてプルマン山に行ってしまうとは夢にも思っていなかった。ひどく寒い冬のある日、ヨンナムは去って行った。<続く>