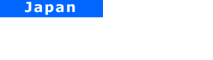また、映画のナレーションと字幕を異なる内容にする手法で「創作された日常」を暴露する。例えば、ナレーションでは主人公の父は被服工場の労働者と紹介するが、字幕では「実は彼は記者だった」と後にわかったことを紹介するという具合だ。
監督はガーディアンとのインタビューで「真の北朝鮮の姿を込めた映画を撮りたかったが、あの国には我々の考えるような日常の風景は存在せず、あったのは『日常の風景というイメージ』だけだった。そこで私たちはその『嘘の真実』を映画にした」と述べた。ところが、この映画に公の場で噛み付いたのは、北朝鮮ではなくロシアだった。監督はロシア政府からの助成金を受け取っていたからだ。