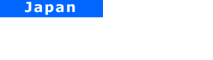教化所に入所して20日過ぎた頃、いよいよ談話(面談)が始まった。保安課の書記が来るというので、保安課に入って頭を下げたままひざまずいて座った。形式的な質問が終わると書記が注意事項を述べた。
「ジュナ、これから教化所生活を送るうえで、罪人たちはもちろん全員だが、保安員たちの行動までよく見て、私に報告しなければならない。特にこれから君を引き受けることになる担当の保安員については、どんなことも見逃さずに記憶しておいて、私がこっそりとお前を訪ねたら来て報告しなさい」他人の仕事を密かに告げ口するのは死んでも嫌だった。けれどもできないとは言えなかったので、返事をせずにためらっていた。
「できるだろう。どうして答えないんだ」
「先生、私はまだ若いし新人です。ここの実情もよく知らないし、他の人が何をするのか知りたくても…」
「いい! 分かったから出て行きなさい!」
保安課の書記が私の言葉をさえぎってしまった。私をにらみつけていると思ったが、挨拶をして出ながらちらっと見たら、目つきは思ったほど鋭くなかった。不安だったが、ほっとした。
だが私はこのために、労働が一番きついとうわさされていた伐木班に配置された。全巨里教化所では、伐木班の人の数が一番多かった。そのため、死ぬ人や体が弱った患者も一番多かった。
伐木班は、担当している保安員も本当に性質が暴圧で荒々しかった。新入班長が夕飯を食べた後、伐木班に連れて行ってくれた。
「伐木班長、この子がジュナです。面倒を見てやってください」
伐木班長は、もう私について知っているというふうに、にっこりと笑った。当時、19歳の収監者は私1人だった。伐木班長は私の罪名を聞くと自分の罪名と同じだと言い、不便なことがあればいつでも話しなさいと言った。よい班長に会ったと思って安心した。
翌日の朝、出力(その日の労働のために監房の外に出ること)して、教化所の庭で担当保安員が来るのを待っていた。背が高い若い幹部が足早に来て、私たちの前に立った。
「新人は前に3歩出なさい」
私と一緒に転房した収監者が2人前に出た。何か聞かれたら、どうやって答えたらよいのか、緊張しながらあれこれと考えていた。重い沈黙が流れた。
頭を下げていたが、何をしているのか気になって頭を上げて、担当の保安員を見た。その瞬間、鋭い視線が私の顔に向けられたことを感じたので、すぐに頭を下げた。
「やあ! こいつ、お前こっちに来い!」
「ジュナ、先生がお前を呼んでいらっしゃる。前に行ってひざまずいて報告しなさい!」
伐木班長がためらいながら教えてくれた。幹部の前にひざまずくやいなや、軍靴が顔に飛んできた。理由も分からずに、しばらく踏み付けられていた。私は悲鳴も上げずに口をぎゅっとつぐんだまま殴られた。担当の保安員はずいぶん長い間私を踏み付けていたが、荒い息を吐きながら口を開いた。
「こいつ、どこだと思って先生の顔を眺めてやがる」
私はとてもなさけなかったが、垂オ訳ありませんでしたと謝った。幹部は伐木班長に向かって大声を出した。
「おい、班長。こいつの罰として、朝まで待機勤務につかせろ!」
教化所では監房ごとに、毎晩待機勤務というのがあった。2人一組になって、1人が監視窓の前に立って、1人は座って罪人たちを見張った。8人が4つの組に分かれて、2時間ずつ勤務した。
夜中に便所や窓から逃走するのを防ぐための措置だった。また、夜間勤務をする幹部たちが監房の前に来たら、監房にいる人の数を報告するという任務もあった。私は幹部の顔を眺めたという罪で、一晩中待機勤務に立たなければならなかった。
その日の夜、待機勤務をする予定った人たちは、「ジュナのおかげでゆっくり眠れるな」と言って喜んでいた。
待機勤務をしながらいくら考えても、担当の保安員がどうしてこんな罰を与えるのか理解できなかった。 一晩中勤務についていたのでとても疲れたが、朝御飯を食べて仕事に出た。
「新人は入りなさい!これから一週間以内に、各自自分の斧と下山ロープ(山で作業した木を引いて下ろすために、体に巻く鉄製のロープ)を、なんとしてでも必ず確保しなさい」
班長の言葉だった。一週間、休憩室で雑用などをしながら、山に行って働くために万全の準備を整えなさいと言われた。教化所に来る前に社会で働いたことがなかったので、教化労働が怖かった。
午後4時頃に、伐木班の収監者を監視するために付いて行った士兵の哨兵が入って来て、休憩室に残って働いていた6人の収監者に、教化班の作業場に行くように指示した。5人が外に出て、哨兵の後に付いて山に向かった。ずいぶん遠くまで行った。
走るように足早に歩いて目的地に着いたが、息をつく暇もなく、木を1つずつ担いで教化所に戻るように指示された。教化班が作業した木のうち、6本が残っていたので、運ばせるために私たちを連れて来たのだった。
担当の保安員は一番太い木を指差して、私に運びなさいと言った。踏ん張って、やっと肩に乗せることはできたが、春の水を吸ったカバノキはとても持って帰れそうになかった。10mも進まないうちに足が震えてきて、肩が割れそうだった。やっとの思いで、はあはあと息をしながら長い時間歩いたが、耐えられずに座りこんでしまった。
「ジュナ、担当の保安員に殴られるぞ。はやく立ち上がって進むんだ」
声が聞こえる方を振り向いたら、伐木班長は私よりも大きな木を担いでいたが、平気そうに立っていた。伐木班長が横で助けてくれたので、また木を担いで歩き出したが、いくらも進まないうちにまた木を落としてしまった。
肩の皮膚がすべてはがれて、口からは臭いがして、のどがつまりそうだった。その時だった。保安員が杖で私の頭を容赦なく叩いた。
「こいつ、早く担がないか。何をぐずぐずしているんだ。早く行かないか」
憎まれ口をたたきながら、殴る手は止めなかった。叩かれないためには、その木を担いで早く進まなければならなかった。どんな精神力が出てその木を担いで走れたのか、今も信じられない。
とにかく、その憎たらしいカバノキを自分一人の力で担いで、休憩室の前に来た。肩から木を下ろした瞬間、知らないうちに泣いていることに気づいた。感情も湧かずむせぶこともなく、ただ涙が流れた。
「血の涙というのはこういうものだ」
悲しかった。母の愛しか知らずに育った私にとっては、あまりにも大きな苦痛だった。これから受けなければならない苦痛を考えただけで目まいがした。私は、この辛い教化生活を勝ち抜くことができるのだろうか。