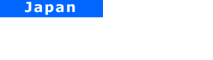母はほうれんそうのお粥を食べながら飴商売をして、少しずつお金を貯めて、2ヶ月に1回面会に来てくれた。本当に両親のもとを去ると、両親の愛がどれだけ大きくて温かいのかということを知ることができる。私はその言葉の真意を、5年間の監獄生活の中で、全身で体験した。
2000年のことだった。
師走が近づく12月のある日、私は新年を迎える前に母に手紙を書くことにした。面会の時は顔を見るだけで、手を握ることもできなかったので、私は母を慰めることができそうな言葉を伝えることにした。
夕方、床に入って鉛筆と紙を取り出し、手紙の内容について思案した。母の力になりそうな文章はなかなか思い浮かばなかった。横になってあれこれと考えていたら、頭の中にその時まで一度も考えたことがなかった、いや考えたくもないあの日の出来事が次々と浮かんできた。
1998年11月26日、友達のクァンイルの誕生日だったので、遊んでから午後1時頃に帰宅した。いつもは「ジュナ」と言って迎えてくれた母が、なぜか横たわりため息をついていた。
「お母さん、具合が悪いの」
「いいえ……」
私は何が起きたのか気になり、何度も聞いた。母はやっと重い口を開いた。
「ジュナ、お前は知らないだろうけれど、キチョル叔父さんに2,000ウォン(当時、北朝鮮の労働者の1ヶ月の月給は70~100ウォン)を貸してあげたことがあるんだよ。1年経っても返そうとしない。これまで何度ももらいに行ったけれども、いつも必ず返すと言うからそのまま帰ってきたんだけどね。でも今日行ってみたら、『俺に金があるわけないだろう』と言って、お母さんを殴ろうとしたよ。しつこく頼むからお金を貸してあげたけれども、返してもらえそうにないね。どうしたらいいかねえ」
母とは遠い親戚にあたるその人を、私は叔父さんと呼んでいた。叔父は生涯酒浸りだった。酒に溺れて、妻や子供に内緒で自分の家の財産を売って酒を買い、家に泥棒が入ったと嘘までついた。そんな叔父を私は普段から無視して、道で会っても見なかった振りをした。
「自分の家を滅ぼしてもまだ懲りずに、今度は私たちまで苦しめようとするなんて……」
母を殴ろうとしたという話を聞いて、私は頭に来てしかたがなかった。母はばっと起き上がる私を制止しようとしたが、「お金を必ずもらって来る」と私が言ったので、それ以上止めることができなかった。当時、2,000ウォンはそれなりの金額だった。
私はすぐに叔父の家に行った。ドアを開けて入ると、叔父の奥さんが私を見て泣きそうな顔をした。
「ジュナ、悪いね。どうしたらいいんだろう。あの人間がまったく、あなたのお母さんのお金までお酒に変えて飲んでしまったのよ。私ももうこれ以上一緒に暮らすことはできない」
「おばさんが私に謝る必要はありませんよ。すべて、あの人が問題でしょう」
私はすぐに、酔いが覚めたようで白目が赤く充血していた叔父を引っ張って、門の外に出た。壁にもたれてタバコを吸っていた叔父に、明日までにお金を返してほしいと言うと、体を傾けたまま近づいてきた。
「こいつ、お前も知っているだろう。叔父さんのどこにお金があるというんだ」
「だったらお金を借りた時は、返すつもりもないのに持って行ったんですか」
「こいつ、母さんと俺の間のことなのに、どうしておまえが割り込むんだ。ちびが礼儀も知らずに」
話は終わっていなかったが、私の拳が叔父の顔に向かって飛んだ。壁に頭をうってつんのめった叔父の頭から血が流れた。
「母のことなのに、息子の僕が関係ないわけないだろう。人のことをよく分かっていな「ようだな」
叔母が走って来て、それ以上殴らないでと言って止めようとしたので、怒りを静めた。
「無条件、明日までに返さなければ殺す」
「分かった。数日以内に必ず返すから」
「いつです」
「10日以内に返してやるさ、この野郎」
10日後に返してもらうと念を押し、私は家に帰って来た。母が苦労して貯めたお金なのに、そのまま着服するつもりなのか。私は家に帰った後も、考えれば考えるほど開いた口が塞がらずに、一人でつぶやいていた。だが、なんということだろう。叔父は意識を失ったまま病院に運ばれた。
保安員(警察)が私の家に来て、こうした事実を伝えた。保安員は私に、自分と一緒に保安署(警察署。韓国の交番にあたる機関は「分駐所」という)に行こうと言った。母の抗議も無視し、保安員は私を保安署に連れて行き、私は控え室という部屋に閉じ込められた。
「叔父さんが息を吹き返せば適当な処分を受けるだけだが、死ねばお前も死ななくてはならない。どうする」
控え室の鉄門を閉めながら保安員が言った。私は叔父が死ぬとは全く思わなかった。別れる時までずうずうしく、10日後にお金を返すから待ってくれと言っていた人が、何で死ぬというのか。またこの前のように、お酒を飲み過ぎて胃痙攣になったのだと思った。夕方の8時になった。ドアが開いて、保安署の部署長が私に出なさいと言った。
「家に行く前に批判書に拇印だけ押して行きなさい!」と言って私を連れ出した。
「やっぱりそうだ。叔父が死ぬはずはない」
そう考えながら部署長に付いて行き、長細い家に入った。保安署の門の前にも行かなかった私は、その建物が何なのか分からずに、部署長の事務室のようだと思って何も考えずについて入って行った。外でちょっと待っていなさいと言って部署長は中に入ったが、また出てきて私に入ってみなさいと言った。
「他の人に拇印を押す仕事を任せたようだ」と思い、ドアを開けて入って行ったら、またドアがあった。控え目にたたいたら、中から入りなさいという声が聞こえた。挨拶をして入ったら、服を脱ぎなさいと言われた。一瞬荒てて、「服はなぜですか」と言うと、前に立っていた保安員が足で蹴ってきた。
「どうして蹴るのですか」
「こいつ、どこだと思って食って掛かる気だ」
「批判書に拇印だけ捺して、家に帰るようにというから来たのですが。私が何の過ちをしたと言って殴るんですか」
「うるさい! ここは罪人を入れる拘留場だ。もう一度叫んだら黙ってはいないぞ」
その言葉を聞いて、仕方なく服を脱いだ。その警護員(看守)は私の服から金属でできたものを全て取りはずしてしまった。胸がどきどきして心臓が震え、何か不吉な頼エがして、言われたとおりに素直に話を聞いた。服を着ると、警護員は私を2号監房に連れて行き、「おい、監房長、こいつは人を殺した殺人者だ。ちゃんと教育してやれ」と言った。
「そんな、僕が殺人者だなんて話にならない。叔父が本当に死んだというのか」
言葉が出なかった。予審(審問、辞書の意味は犯罪の事実などを明らかにする訴訟行為)を受けた時、私は叔父が壁に頭をぶつけた後地面に倒れた時に、土にめりこんでいた尖った石で頭をうって、病院で4時間後に死亡したという事実を知った。
後悔と反省で苦しみ、5ヶ月にわたって予審を受けて、私は朝鮮民主主義人民共和国刑法第145条第2項 <過失的重傷の殺人> という罪で、7年の刑を言い渡された。叔父の死亡の鑑定結果は「脳出血による死亡」だった。
寒い冬に母は、唇が青くなり、手の甲はかちかちに凍ったまま、私に暖かいご飯を食べさせようと、お汁とご飯を懐に入れて温めながら、保安署の鉄門の前で長い時間待っていた。辛そうな顔は見せずに面会に来る母に、せめて手紙で慰めの文章を渡したいと思い、ペンを執った瞬間停電になった。私はぶつぶつ言いながら、明け方に起きて書こうと思って床にふせった。疲れていたため、起床の銃の音を聞いて起きた。他の人の目も気になり、結局手紙を書くことができなかった。