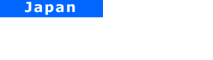中国に来て13年経った。最近は、パソコンの電源を入れるたびに韓国のサイトを見ている。はやる気持ちを抑えて、「脱北者同士会」や「デイリーNK」のサイトで、北朝鮮に関する記事を読みつつ、故郷の人たちの名前を探したりもする。彼らのことを思う度に、ため息とともに涙が溢れる。
私は1970年代末に、両江道の普天(ポチョン)郡の青林里(チョンリムリ)という村の平凡な農場員の家庭に生まれた。青林里は前後にそびえる山と、山の間を流れる小さな小川にはさまれた村だった。幼い頃、村の労働党書記のおじさんは恐ろしい人だと思っていた。人民学校(小学校)に通っていた時、父親が目の周りに真っ青なあざをこさえて帰ってきた。党書記に殴られたのだと母に話しているのを聞いた。その時から私は、党書記や幹部を見ると、遠くに虎を見つけたかのように、腰を抜かして逃げていた。
アヘン農場という愚かな幻想
(大飢饉の)苦難の行軍がやってくる直前の1993年、青林里全体が白桔梗(ペクトラジ)農場、つまりアヘン農場に変わった。農場からの(作物の)分配が足りず、いつも副業の農業に頭を悩ませなければならなかった青林里の人にとっては、嬉しい知らせだった。
アヘン農業さえうまくいけば、もう農場の分配だけではなく、国から直接白米の配給をもらえるようになり、優待供給として毎年2着分の服の布地、食用油、そして農場全体にテレビがタダで配られるうわさが広まったからだ。
その年、山里の村の畑は、白いアヘンの花に覆われた。私たちは生まれて初めて、協同農場の分配でなく、国がくれる白米を受け取った。
1994年、アヘン農業で利益を得た人たちが、副業の農業をすべてやめて、畑を農場にしてアヘンを植えるようにしてほしいと頼んだ。その年の7月に金日成主席が亡くなり、哀悼の雰囲気が全国に広がった。
「悲しみを力と勇気に変えて、社会主義強盛大国の建設に向けて更に頑張ろう!」というスローガンが、あちらこちらに貼り出された。日照りと洪水で全国で農業が台無しになったと騒いでいたが、うちの村のアヘン農場は大豊作だった。
青林里だけでなく、隣りの内曲里(ネゴンリ)、虎山里(ホサンリ)、儀化里(ウィファリ)でもアヘンは豊作だった。うちの村の人たちは、じきに用意されるであろう分厚い札束と下賜品を思い浮かべ、派手な幻想に浸っていた。
死の行進「苦難の行軍」
だが、アヘンを収穫した年の11月から、国が農民に対する配給を中断した。国からの配給を信じて農作業を一切しなかった人たちが、あちらこちらで飢えて倒れ始めた。
党書記のおじさんが、普天郡と両江道の労働党に食糧をもらいに行ったというううわさだけが広まった。11月末に、食糧が到着したという知らせを聞いて、皆が配給所に駆けつけた。飢えて学校に行くことすらままならなかった私も、配給をくれるという話を聞きつけ、母と共に配給所に向かった。
その日、配給所では2号物資(戦争物資)の倉庫から持って来たという、凍ったジャガイモと麦豆を、1ヶ月分を受け取った。配給所で党書記のおじさんは村人に向かって「自然災害で農業がだめになったら、いつ食糧が入って来るかわからない。本当に大切に食べなさい」と言っていた。
その年の12月。何台もの車に分乗した多くの兵士たちがやってきて、村の向かいと裏の山の木を切り始めた。中国に売り払って、兵士たちに食べさせるコメを取り寄せるのだという。
死を覚悟して軍の車に立ちはだかる党書記のおじさん
その日、母と私は、50里(20キロ)以上も離れた郡の市場に行って、家に取っていおいた布地2着分や犬の毛皮などを売って、コメを少しだけ手に入れた。村の中心にさしかかると、血だらけになった男性が、丸太を乗せた兵士たちの車を遮るように立っていた。党書記のおじさんだった。
「村人たちは飢え死にしている。木を切るのならば、コメを出しなさい!コメを出さなければ木を1本たりとも着ることは許さない」
車の前に立ちはだかる党書記のおじさんに兵士たちが容赦なく殴りかかった。村人たちは地団駄を踏みながら涙を流していた。軍の安全部から新たに配属された担当の駐在員(警察)が駆けつけて来て、ピストルを威嚇発砲した。銃声に驚いた兵士たちが後ずさりすると、1人の軍官(将校)が、紙切れを掲げた。
「さあ!将軍様(金正日総書記)のご命令だ。兵士たちは食べてこそ、国を守れるのではないか。将軍様のご命令に拳を突き出す奴がいれば前に出ろ!」
将軍様という言葉を聞き、誰もが言葉を失った。その時、党書記のおじさんがよろけながら立ち上がった。
「この丸太は国の財産であり、我々の農場の財産でもあります。結構です。将軍様のご命令なのであれば持って行きなさい。代わりに、この農場の丸太を切って行くという承認状を持って来なさい」
軍官は、懐から別の紙切れを取り出し、党書記のおじさんに突きつけた。軍の山林経営所が発行した丸太の受領書だった。おじさんはそれを受け取るや、破いて捨ててしまった。
「あなた方はさっき、将軍様と言いませんでしたか。こんなものではなく、将軍様の署名の入った受領書を持ってきなさい」
党書記のおじさんの堂々とした姿に、軍官たちも軍人たちも呆然として言葉を失った。軍官は、何やらおじさんに頼み込み、腕を掴んで党事務所に連れて行った。
かくして、軍と青林農場の間である種の契約が結ばれた。それは次のようなものだった。
「青林里に来て丸太を運送する車は、1台当たりトウモロコシの粉4袋(80キロ)を差し出すこと」 「木を切って積む仕事は農場員が行い、彼らの食事を保障すること」
こんなやり方でも食べ物を確保できたのは、うちの農場だけだった。他の農場は山を丸裸にされ、あちこちに禿山が現れた。
その年の冬、電気も来ない寒い家で、うちの家族は布団をかぶって、餓死するのを待つばかりの生活を送っていた。
党書記のおじさんが毎朝、家々を周り、お湯に溶いた炒り粉を配って歩いた。さらに、軍のトラックに切り出した丸太を積んでいる若い人たちを動員し、飢えて動けなくなった人々の家に、薪を運ばさせ、自分の手で火をくべてくれた。