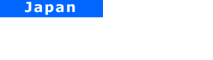李明博政府の出帆前後に多くの市井の世論で、”最低限、親北朝鮮左派政権が終息したということ、それ1つだけでも今回の大統領選挙はあまりにもよくできたことではなかったか? “、”天が無情でなかったから…”、”もし今回も左派に移っていたら、その時は本当に大韓民国は万事休すではなかったか?” というはらはらする危機感と、“ふう~っ”という安堵感が同時に噴き出した。
そのため、多くの国民は李明博政権が時々過っても、少なくとも‘過去10年’間の紅衛兵のでたらめな世の中よりは数段国らしい国を作ってくれるだろうという期待をまだ持っている。そして、そのような李明博政府が何としてでも‘左派10年’の失敗を跳躍する著しい‘成功政府’になるように助けてあげ、押したいという善意にもまだ大きな変化はない。だが、世論のこうした善意と信頼をこの数日の間、急に激しい混乱と混同の中に突き落とした一連の怪しげな事態が発生したことについて、李明博政権は果してどのような言葉でどのように説明するのだろうか。
表に現われた現象は、単に古い不動産の過多所有と、それに対するあさましい‘言い訳’でもない‘3流コメディー’レベルの発言だった。問題はこうした3流コメディー水準の発言しかできない人たちが、一体どのようにして‘先進化’を云々する政権の国務委員に抜擢されたのかということだ。
そのようになった事情の根源は、たった一つである。それはまさに、李明博チームの‘過って理解された実用主義’と、‘過って使われる実用主義’だ。
実用主義とはピアース(Peirce)、ジェイムズ(James)、デュイ(Dewy)以来のアメリカ的成果主義の哲学の伝統だ。そこには“お金が全て”だとか、“価値は問い詰めるまでもなく、きじを捕るのは鷹”という浅薄な没価値的取得の動機があるだけでなく、カント以来の真摯な真理(truth)追究の方法論的苦悩がおさえつけられている。
これを世俗的な政治スローガンとしてつまみ出したのが、外でもない中国の鄧小平の黒猫白猫論だった。これは私たちの実学派の先覚者たちの実事求是哲学と決して比較することができない、文字通りの政治煽動スローガンに過ぎない。
“黒猫でも白猫でも鼠さえ捕ればよい“という彼の実用主義は、結局‘不変の原則’をはなれてしまい、単なる便宜主義的普及闘争の名分に過ぎなくなった。彼は結局、マルクスやレーニン、毛沢東の大原則から去ったところまではよかったが、市場経済は戦闘的自由の理念の下でのみ整合性を有するという、正統な自由主義の哲学的大原則にも詐汲?ュいたのであった。
彼の中国はそのおかげでもちろん急速に発展している。だが、哲学的精神的基礎を弾き出した鄧小平の道具的実用主義は、今日の中国を日本の民主党の指導者である小沢氏が直撃弾を飛ばした通りに、甚だしい腐敗の奈落に追いたてている。まさに実用主義に対する誤った理解の終着点であるというわけだ。
李明博政府のリュ・ウイク大統領室長は、その延長線上で“南北間、そして南南間にイデオロギー的是非は不必要だ”と言った。これは鄧小平の黒猫白猫論を一層‘真水’に脱色させた社会科学的、哲学的無知の決定版だった。リュ・ウイク室長がその言葉を金正日にしたのであれば、それなりに見過ごすこともできる。朝鮮半島で百百教のようなでたらめな理念を説破する人は金正日しかいないからだ。
だが、彼は南北間と南南間の理念闘争も不必要だと言った。つまり、大韓民国の右派に対しても“あまり理念の戦いに没入するな‘という‘両非論(対立する2つの言葉がどちらも誤っているという理論)’が含まれている。本当にそうであるならば、民労党のPD系列の従北主義の批判もするなということなのだろうか。私たちは金正日の人権抹殺にも黙らなければならないということなのか。非転向長期囚は無条件北送しても、国軍捕虜と拉致被害者に対しては一言も発してはならないということなのか。そして、韓国の主体思想派である一心会のスパイ行為に対しても、ただの一言も批判してはならないということなのか。リュ・ウイク室長ははっきりと解明しなければならないだろう。
李明博政権の人事問題などの一連の不協和音は、結局李明博チームの‘純正実用主義’ ではない、‘没価値的実用主義’から始まった必然的な所産であるといえよう。
そのためか、リュ・ウイク室長は“この10年は失われた10年ではない”と言った。それならば、今までの10年を‘失われた10年’と前提して反左派血闘を展開した、5年間の正統右派とニューライトの立場は一体何だったというのか。彼らは再び、風餐露宿する原野自由主義の戦士として、あの刺々しい野党闘争の道を歩まなければならないというのだろうか。