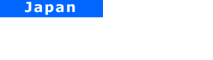北朝鮮の歴代政権は、声を上げる民衆を無残に虐殺し続けてきた。政権の理不尽な行いに抗議した黄海製鉄所の労働者らを、金正日総書記は戦車部隊を派遣して轢殺した。
(参考記事:抗議する労働者を戦車で轢殺…北朝鮮「黄海製鉄所の虐殺」)一方、韓国にもまた、国家が国民を虐殺した暗い歴史がある。
昨年、韓国で1200万人を超える観客を動員した映画「タクシー運転手 約束は海を越えて」が日本でも公開され、話題を集めている。映画の舞台となったのは、今から38年前の1980年5月18日から27日にかけて起きた、「5・18光州民主化運動(光州事件)」だ。
絶大な権力で国民の民主化要求を押さえつけてきた独裁者、朴正煕大統領(後の大統領・朴槿恵氏の父)が1979年10月26日に暗殺されて以降、韓国社会では民主化への期待が漂い、「ソウルの春」とも言われた。ところが、クーデターを起こした全斗煥少将(後の大統領)は、翌年5月17日に戒厳令の適用範囲を全国に拡大し、民主化運動を暴力で押さえつけようとした。
市民はそれに反発、各地で激しいデモが起きたが、全羅南道の光州市では戒厳軍が市民を武力で鎮圧するだけではなく、デモとは関係のない市民や子どもまで虐殺した。政府が公式に認定しただけでも、現場での死者165人、後遺症による死者が376人、行方不明者76人、負傷者3139人という膨大な犠牲が出た。実際の犠牲者数はこれをはるかに超えると言われている。
北朝鮮の国営メディアは、この光州民主化運動を事あるごとに取り上げている。
北朝鮮の朝鮮労働党機関紙・労働新聞は昨年12月21日の紙面に「光州を血の海に鎮めた極悪な殺人魔」と題した記事を掲載。戒厳軍が光州爆撃を検討していたことを示す資料を韓国の5.18記念財団が発見したことに触れ、「これは社会の自主化と民主化、祖国統一のために立ち上がった光州の抗争勇士たちを獣のように弾圧、虐殺して、光州市全体を血の海にした張本人が米国であることを、否定できない歴史的事実として再び明確に裏付けした」と述べ、弾圧の背後に米国がいたとの見方を示した。
同事件を巡る「米国責任論」の是非についてここでは論じないが、多くの市民を虐殺した全斗煥氏らの責任については議論の余地がない。しかし北朝鮮に、韓国の過去の政権が行った犯罪的行為を批判する資格はあるのだろうか。
冒頭で述べたように、北朝鮮の歴代政権は、数多くの国民を無残に殺した。たとえば、1990年代後半に起きた北朝鮮最大の大粛清「深化組事件」では、高級幹部のみならず一般住民に至るまで2万5000人が処刑または追放された。
(参考記事:血の粛清「深化組事件」の真実を語る)それ以外にも、未確認ながら1976年に黄海南道(ファンヘナムド)の海州(ヘジュ)で、暴動の弾圧で3万人を虐殺したとの情報もある。
(参考記事:繰り返された「抵抗」と「虐殺」…北朝鮮の血塗られた69年史)韓国も北朝鮮も、政府が罪のない国民を虐殺した過去を持つが、両国の最大の違いは、真相究明と責任者の処罰だ。
韓国は金泳三政権時代だった1995年12月、光州民主化運動の真相究明と責任者処罰のために、5.18特別法を制定し、その法律に基づき全斗煥氏ら16人を逮捕・起訴した。全斗煥氏は一審で死刑判決、二審で無期懲役判決を受けた(その後恩赦で釈放)。さらに、今年2月には「5.18民主化運動真相究明特別法」が成立し、政府、光州市、学界、メディア、市民による真相究明のための努力が続けられている。
一方の北朝鮮では、虐殺の責任者である最高指導者の責任が問われることはない。韓国には、北朝鮮人権記録保存所が作られ、北朝鮮で起きた人権侵害事例をデータベース化する作業が続けられているが、政権が崩壊しない限り、真相究明や責任者の処罰が行われることはないだろう。
いま、金正恩党委員長は非核化の「見返り」として体制保証を求めており、米国も韓国も、それに応じる構えを見せている。
朝鮮半島の非核化は地域の平和のために必要なものだが、それと引き換えに、北朝鮮が行ってきた人道に対する罪が追及されないとすれば、実に皮肉なことだ。
(参考記事:今も続く北朝鮮「冷凍拷問」の恐怖…いずれ断罪の日が来るか)高英起(コウ・ヨンギ)
1966年、大阪生まれの在日コリアン2世。北朝鮮情報専門サイト「デイリーNKジャパン」編集長。北朝鮮問題を中心にフリージャーナリストとして週刊誌などで取材活動を続けながら、テレビやラジオのコメンテーターも務める。主な著作に 『脱北者が明かす北朝鮮』 、 『北朝鮮ポップスの世界』 (共著) 、 『金正恩 核を持つお坊ちゃまくん、その素顔』 、 『コチェビよ、脱北の河を渡れ ―中朝国境滞在記―』 など。