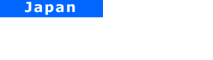2026年1月に発生した平壌へのドローン侵犯事件は、南北関係の力学を決定的に変える転機となり得る。発端は、平壌上空に無人機が侵入したと北朝鮮が発表したことだった。当初、韓国政府は軍の関与を否定し、責任回避に終始した。
北朝鮮の金与正氏は、無人機問題を「主権侵害」と断じ、韓国を激しく糾弾する談話を発表。再発すれば報復も辞さないと警告した。しかし韓国側は、これを「非難もコミュニケーション」「対話の兆候」と楽観的に解釈する。確信犯的に警告を融和のサインに読み替えて、主導権を北朝鮮に差し出す形となったが、金与正氏は追加談話で、韓国への苛立ちをあらわにした。
その後、韓国は調査の結果、軍の関与を認め、統一相の鄭東泳氏が「遺憾の意」を表明するに至る。金与正氏はこれを即座に「公式の謝罪」と評価した。だがそれは対話の入口ではない。許す側と許される側という上下関係を刻みつけ、心理的・政治的主導権が平壌にあると内外に示すための演出にほかならない。
南北対話がすぐに再開する可能性は低い。しかし、今後何らかの衝突やトラブルが起きた場合、この“序列”は前提となりうる。北朝鮮は「謝罪を引き出した側」という立場に立ち、韓国は再発防止や信頼回復を求められる側に回った。つまり、交渉の主導権はすでに平壌に移ったのである。
結果として韓国の対北政策はさらに混迷する。強硬にも対話にも踏み切れない曖昧さが露呈し、残された選択肢は限られる。まもなく開かれる第9回朝鮮労働党大会で「断韓政策」が鮮明化すれば、核・ミサイル問題を含む北朝鮮問題で韓国の存在感は一段と後退するだろう。