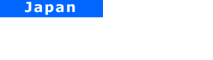病気の治療は終わったが、家族の重荷になることが垂オ訳なく、1人で生活費くらい稼ごうと、思い病気が再発して死の峠を越えたが、体も全快した頃、私のためにくたびれはてた母は長女の家に行き、出勤する弟と、まだ体が回復していなかった私に幼い甥たちを任せて、本家に行って来ると言って出た義理の妹はひと月経っても消息もなく、心が痛んでお酒を1杯飲んだ。「2回も生かしてあげたのだから、これからはお姉さん1人で生きてほしい」と泣いて頼むように言った弟の声…。
私が大変だったくらい、みんなも大変だっただろう。私が痛みを感じていたのと同じようにみんなも痛みを感じていただろう。それでも病気にかかった私は、あの人たちのために何もできなかったが、どうしたらよかったのだろう。私があの人たちのためにできたことはただ1つ、そばを離れることだった。
そんな体で大丈夫なのかと心配する弟と別れの挨拶を交わして出たが、あてもなくあちこちさまよったあげく、遂に自鮪ゥ棄の心情で豆満江の川辺に立った時の私の姿は、本当に見かけだけ残った「生けるしかばね」のようだっただろう。
そこで大切なものを全て捨てた。捨ててはいけないことは分かっていたが、そのまま抱いて行けば重い荷物になって、豆満江に入る私の両足首を捕まれるかと恐ろしくて、その瞬間だけは捨てた。
「私には誰もいない。両親も兄弟も親戚も親友もいない。この世の中に誰もいない私。そう、私は寄る辺も頼る所も何もない孤児だし、独り身なので行くのよ…」豆満江の向こう側からこちら側に越えた、私の人生を完全に変えたその2分間、自分に向かって何度も何度も言ったのはただこの言葉だけだった。
一緒に手を取り合って豆満江の水に入った19歳の子が怖いと言ってすすり泣く。怖いなんて、何が怖いというの。すべて捨てて行く人に恐れるものがあるだろうか…。
「お前、これくらいのことも考えられずに来たのか? 泣くな」小さくつぶやいたきつい自分の声に泣き止んだ。そうだった。何の未練も恐怖もなかった。死を覚悟しなければならないその瞬間だけは、大切な私の命のことも考えなかった。
そうやって越えて来たのだった。私の故郷の最後となった豆満江を…。すべて捨ててがらんとした胸には、「死なずに生きなければならない」という一言だけがぽつんと残ったまま…。ぎゅっとつまった氷に辛うじて残っているその一言が、川辺に立った私にとって人生の目標になった。
一度葬ってしまった大切な思い出をまた取り出す機会は、送還の危険が影のように付きまとった中国では一度も来なかった。一生懸命働きたくても働く所がなく、どこに行っても脱北者に送られる不信と危険のにらみに耐えられなかった日々…。
汚い肉欲を満たそうとして、言うことを聞かなければ告発すると脅す人たちを避けて、朝鮮族だと嘘をついてやっと就職した会社。一生懸命働いて社長のお婆さんの愛を独り占めした私が目障りで、北朝鮮の女だとささやいて公安に告発しなさいとそそのかした朝鮮族の人たち。それでも私はどうすることもできずに、ただ一人トイレで顔がむくれるまで泣いた。
行く所がないのにどうしたらよいのか。これ以上、どこに行ったらよいのか。もう避けたくはなく、逃げたくもなかった。この貧しい命をこれ以上つなごうとばたつかずに、このままここで終りにしてしまおう。だが天が見ても私の運命があまりにも苛酷に思えたのか、思いもよらず牧師様が来て人を捕まえることしか頭のないあの人たちの気持ちを鎮めてくれた。わけは知らない牧師様の両手をしっかりと握って、「来てくださってありがとうございます」とつぶやき続ける私の目からはとめどもなく涙だけが流れた。
それが中国での私の生活だった。絶望の末に、韓国に行くことができるという友人の紹介を聞いて、1泊2日汽車に乗ってめくらめっぽうやってきたが、そこで私を待っていたのはまた別の送還の危険と、先が見えずに待たなければならない時間だった。
とても親切だった人が自分の肉欲を満たすことができず、公安に告発すると脅かした瞬間、我慢して堪えていた怒りと恨みが爆発して、そこを走って出たが行く所はなかった。
守ってくれる国もなく、死んでも振り返る人もいない私は通りをさまよい、強く風が吹き荒れる海辺で荒い波を眺めながら胸をよぎったのは、あの中には果して私の居場所があるのだろうか、こうして生きようと死の峠を越えてここまで来たのではなかったのかということだった。
豆満江に葬ってしまった過去の私の人生。痛みを感じた辛い思い出も多かったが、それでもそれはいつかまた取り出して、胸の中に抱かなければならない大切なものだった。(続く)