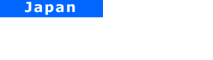朝鮮でも平壌の一流大学に入ることは’夢のまた夢’の難しいことだ。勉強もよくできなければならないし、家の成分にも問題があってはならない。
筆者は何のバックもなしに実力で望んだ大学に堂々と入学した。大学合格の通知を受けた時は、世の中のすべてのものが私のものになるような希望で一杯であった。しかし、楽しい大学生活はあまり長続きしなかった。筆者の大きな抱負に水を差したことの一つが、閲兵式の参加だった。
大学に進学してから3日ぶりに、閲兵式の参加者に選ばれた。結局、筆者の大学生活は‘完全無欠な人が病身になって出る’という閲兵式で始まった。閲兵式といえば、南朝鮮の同胞たちは学校の行進の訓練程度に考えるが、朝鮮で閲兵式は1年間の軍事訓練を彷彿とさせる残酷な訓練だ。
朝鮮では金日成、金正日の誕生日と朝鮮人民軍の創立記念日、朝鮮労働党の創立記念日などに学生、労働者、軍隊、一般の市民たちを動員して、金正日に忠誠の念を誓わせる閲兵式の行事を行う。観客はただ金正日一人だ。金正日一人を満足させるために数多くの人々が一年中血の汗を流して行事を準備する。
大学生の閲兵式の参加者を選抜する基準はたった一つだ。それは’背’である。閲兵式の参加が決まった大学では、学生たちを一つの席に集めて、‘背比べ’を始める。私は背が特に低くはなく、新入生という理由で、すぐに選抜された。閲兵式というのをテレビでもたまに見た私は、近付く訓練がどれほど辛いものであるか、全く予想することができなかった。
私のいた大学が1個縦隊を引き受けることになった。1個縦隊は全部で12の横隊からなっている。一つの横隊には25人が立つ。1横隊には背が一番高い学生が組み込まれ、12横隊には背が一番低い学生が立つ。
党幹部の子供は訓練から外され
各縦隊には縦隊の責任を負った大隊長がいて、その下に政治部大隊長、後方部大隊長がいる。またその下には中隊長、政治部中隊長がいて、その次の横隊長たちと副小隊長、秘書たちがいる。1個横隊も3個の分隊に分けて、分隊長がまたいる。こうした幹部は普通4年生や3年生が引き受ける。各縦隊で幹部ではない学生は、大部分が新入生だ。
最初の訓練が始まった時は、大部分の学生は笑って騷ぎながら、‘実際に将軍様が私たちを見に来るか’などと話しながら時間を過ごした。しかし、翌日から一人、二人ずつ、訓練から抜ける人がでてきた。
当時は閲兵式に参加することができない事情があるのだと思った。後になって分かったことだが、訓練から抜けた人は皆、幹部の子供たちだった。彼らは一様に体調が悪いという言い訳をした。結局、‘背比べ’で始まった閲兵式の隊伍の選抜は、1年生の学生と地方から上京した貧しい寮生たちに確定した。
一つの大学が1個縦隊を構成するため、閲兵式に選抜された学生たちは、午前は講義を受けて、午後には学校の運動場に集まって訓練をする。学校の運動場の埃をすべて吸い込んで訓練すれば、夕方には口の中に砂がたまるほどだった。
閲兵式の訓練の最初の段階は‘体の力をぬくこと’と、‘足の端を伸ばすこと’だ。芸術体操の選手たちの訓練をそのまま再現したような訓練だが、毎日訓練の課題が提示されて、課題を遂行することができなければ訓練が終わらなかった。
最初の月は大学の運動場で訓練をして、翌月からは主体思想塔の教養の庭の下で訓練をした。その頃から一部の学生は足に関節炎ができはじめる。講義の時間に押し寄せる眠気に堪えることができず、教員に叱られることが頻繁になり、患者が更に増えた。いくら体が痛くても訓練に出なければ厳しく追及された。
主体思想塔の街灯、全て割ってしまいたい
毎日午後2時から始まる訓練は普通7時に終わるが、訓練が終われば縦隊訓練の教員が訓練の総括をする。その時指摘された学生たちは、その縦隊で非難の対象になる。縦隊総括が終われば縦隊ごとに総括をする。
縦隊の総括では訓練の時間に遅れた人、訓練に不真面目に参加した人、訓練で指摘を受けた人々を厳しく批判する。縦隊の総括が終われば小隊、分隊の順に総括をする。
小隊の総括も厳しい。小隊の総括が終われば分隊別に集まるが、分隊長は翌日の訓練に遅れてはならず、訓練にまじめに参加しなければならないという点を強調して総括を終える。小隊の総括が終わるには、普通1時間半かかる。しかし、総括が終わっても、一日の訓練が終わるのではない。
総括で指摘を受けた学生たちは、夜の9時に再び補充訓練をしなければならない。あの時のように主体思想塔の公園の街灯の明りが恨めしいことはなかった。街灯の明りがなければ、補充訓練もなかったはずだという考えが頭から去らなかった。誰かが見ていようがいまいが、石を投げつけて全ての街灯を割ってしまいたかった。
寮の学生たちがくたびれた身を引きずって大学の寮に帰るには、普通歩いて30分~1時間かかる。その時間にはバスもないから、また歩かなければならない。寮の夕食は既に終わり、夕飯を食べることもできない。
足がむくむく腫れ上がり、眠れず
飢える苦痛よりもっとつらいのが、‘水’がない苦労だ。寮では水が出ないから、洗濯は二の次にして、洗顔も思うようにできない。一日中埃を被っていたから、到底そのまま寝床に入ることもできない。そこで、数人ずつ大学の周辺のアパートの前にある水ポンプを探す。顔を洗ったら夜11時過ぎになる。
寝床に横になったら、まるで全身が土の中に消えるようだった。しかし、まともに深い眠りにつけない。いくら冷水で洗っても足がむくむく腫れて熱が出て、深く眠ることができなかった。
今になって考えると、それでもここまでは幸せな時間だった。酷暑が始まる前の苦労は、苦労とは言えなかった。夏になると午前の講義さえも聞けずに、一日中訓練に出なければならなかった。
平壌は6月には蒸し暑くなる。更に、私たちの訓練場だった主体思想塔の教養の庭は、木一本ないコンクリートだ。熱い陽の光がコンクリートを熱く焼き、休む時間も腰を据えることができない。
いくら暑くても、厚い制服のボタンをはずすことができなかったし、帽子も脱ぐことができない。背中をじっとりと濡らした汗のしずくは、いつのまにか白い塩に変わり、体の中からにおいが上がってきた。洗濯もまともにできなかったから、私の体の汗のにおいがそんなに疎ましいものであるということを、その時初めて知った。
閲兵式の訓練は休日も与えられない。一日でも休めば、足が固まるといって日曜日もずっと訓練をさせた。あの時一番憎かったのは、親の権力のおかげで訓練には参加しないで、’保障組’に属して遊んでばかりいた学生たちだった。
‘保障組’というのは、閲兵式の訓練に必要な条件を作るために、縦隊ごとに15人程度の保障の者たちを置く特別な組だが、訓練する学生たちのためにする仕事は一つもなく、訓練の指導教員の使い走りや、酒のテーブルを整えることが彼らの任務だった。
閲兵式で足と腹部がよじれる
初めから訓練の隊伍から外されるほど親のバックが派手ではないが、ある程度お金と権力を持っている中間の幹部の子供が、‘保障組’に属することになる。
閲兵式の隊伍の標準の歩幅の長さは70cmだ。‘120歩の奏楽’に合わせてつま先をきれいに伸ばして、両足を地上から60cmまであげなければならない。一歩進んで地面を勢いよく蹴りながら、その反動で他の足を持ち上げるのだが、全身の力を込めて勢いよくコンクリートを一日中蹴り上げると、内臓がよじれるようだった。
私たちは閲兵隊内で機械のように動くことを要求された。事実上、私たちは機械だった。政治部隊長や政治部中隊長は休みの時間ごとに訓練隊伍の前に出てきて、“行事を死守するという徹底した意志を持てば、肉体的苦痛は軽く乗り越えることができる”と、たわごとを言った。
閲兵式の準備は足と腹部をよじれさせるだけでなく、頭の中までよじれるようだった。朝の7時30分に縦隊の隊列の検閲がある。その時、首のカラーやズボンのしわ、縦隊のマーク、ベルト、ボタンなどをきちんと身につけているか検閲して、縦隊ごとに座って労働新聞の社説や金日成・金正日の偉大性についての資料を読む。そして訓練の休み時間ごとに、政治教育事業を行う。体も頭も休む間がない。
一月に一回くらい、閲兵式の訓練の総指揮部で組織する訓練の検閲があるが、そのたびごとに訓練の厳しさが倍になる。金日成広場の前の道の長さは216mだ。金正日の誕生日、2月16日を記念するために216mに作ったのだ。閲兵式の参加者は、216mの距離を1分40秒以内に通過しなければならない。1分40秒! ふと見たら非常に短く思えるこの瞬間のために、数千時間練習しなければならなかった。
最初の訓練から半年ほど経つと、私たちは4.25旅館に入所した。冬が訪れようとしていた。4.25旅館に入所する時、訓練用の冬の綿入れや靴など、すべてのものを学生たちの自費で購入しなければならなかったが、冬服とベルトを求めるのが本当に大変だった。
4.25旅館は平壌市のサドン区域のソンシン洞にあるが、国家の行事や会議に動員される人々を収容するために立てられた旅館だ。外国人の目にはみじめに見えるが、それでも朝鮮では4.25旅館の施設は、相対的に非常に高い水準だ。
一部屋当たり100人で生活しなければならないが、朝鮮の基準では最新の設備だった。そして食事の質もとても高かった。大学の寮でトウモロコシ飯をひとさじ食べて訓練した私たちにとって、雑穀飯と豆油が浮かんだ白菜のスープは、すばらしいご馳走のように思われた。一週間ごとに卵が1個ずつ出され、毎日キャンディーも15個ずつ、おやつとして支給された。