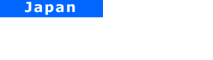※この記事には、性暴力の被害に関する具体的な記述が含まれています。
韓国に来てわずか数ヶ月だったころのことだ。北朝鮮文学の教授が、私に確認でもするかのようにこんな質問を投げかけてきた。
「北朝鮮に性暴力はないでしょう?」
性暴力?韓国に来て何度も聞いた言葉ではあったが、まだ耳に疎かった。だが、その意味合いは推測できた。後に付いていた「暴力」という2文字のためだった。
「はい、ありません。北朝鮮では生活総和制度が厳格なのに、そんなことをして生きていけますか?」
そう答えた私の心は、性暴力がなく、女性として体を純潔に守ることができる社会から来たという自負心のようなもので満ち溢れた。
だが、韓国で暮らすようになってから3年ほど経ったころ、その自負心が突如として吹き飛んだ。北朝鮮で遭った性暴力の記憶が思い出されたからだ。大学院に通って1年半。被害事実の具体的な形象を認知して、最悪だった健康がある程度回復したころだった。
「労働党員になりたい!」
平壌の第2自然科学院(国防科学)出版社で筆事工として働いていた時のことだった。平壌新聞で初めてとなる詩を発表した私は、出版社で脚光を浴びる存在となった。そのころの私は、社会に第一歩を踏み出してから始まった、労働党に入りたいという熱意に囚われていた。
「どうすれば栄光の朝鮮労働党員になれるだろうか?」
長い思索の末にたどり着いた答えは、当時行われていたチュチェ(主体)思想塔の建設現場に、個人的に食糧を届けるというものあった。1年半もの間、昼食を抜きにして集めた50キロ分の食糧券を党組織に差し出し、チュチェ思想塔の建設現場に私の名義で届けて欲しいと伝えた。
だが党書記は、「それよりも、人民班の配給所で(食糧を)受け取り、領収証を党組職に差し出すのがいいだろう」と助言してくれた。当時の北朝鮮では党全体で食糧受配事業を猛烈に行っており、党のイルクン(幹部)の事業の成果は、彼の下にいる機関の従業員の、食糧を受け取った量で評価されていた。
初級党書記の本音を悟った私は、まっすぐにご飯工場に行き、食糧券を蒸しパンに変えた。湯気の立つ蒸しパンの入った大きなかばんを両手に抱え、出版社の隣にあった「チュチェ主体思想塔建設突撃隊江原道旅団指揮部」の政治分科に全て差し出した。
そこで働いていたイルクンたちは、私の行動に感嘆した。炊事員を呼んで、ご飯と肉がたっぷりはいったスープで私をもてなし、かばんには高級干し魚をいっぱいに詰めてくれた。父が(日本の植民地支配からの)解放後に初めて味わったというあの高級干し魚だ。さらには、私の支援のことについて、出版社の党委員会に知らせてくれた。適切に評価してやってほしいということだった。
成功を夢見る女性を狙う黒い影
出版社の初級党書記は、入党の対象として私に目をつけた。そして私を呼びつけた。細胞書記に導かれ、彼の部屋に入った。窓辺を夕闇が包み込もうとしていたころだった。当時の定時退社の時間は午後10時だったので、特におかしいとは感じなかった。停電で電気が消え、部屋の中は人影がようやくわかるほどに暗かった。
細胞書記が初級党書記に、「チェ・ジニトンムを連れて来ました」と報告したところで、電気が消えてしまった。手持ち無沙汰に立っているのが気まずかったのか、「私は帰ります」と言い残し、部屋から出ていった。初級党書記は慌てた様子で、「そうしなさい」と彼を帰し、「なんで停電になったんだ」とつぶやきつつ外に出たが、2分もせずに戻ってきた。
私は緊張した。彼が私のそばに近寄ってきた。
「君は最近、どう暮らしているのかね」
彼特有の舌足らずな声で尋ねてきた。同時に、彼の手が私の首筋に触れた。社内で噂が立つほどの貧乏暮らしだった私のことに、何ら興味を示さなかったのに、なぜ今更。どう受け止めればいいのか見当もつかなかった。
やがて彼は、私が確かな決断を下して、適切な対処をするしかない行動を加えてきた。震え声とともに、彼の大きく力強い手が、私の胸を押さえつけたのだった。「あっ!」と悲鳴を上げた私は、ドアを勢いよく開けて、部屋を飛び出した。
ちょうど、初級党秘書を追い落とす口実を探していた副社長が、その一部始終を目撃していた。私の意思とは関係なく、初級党秘書は解任された。彼は、出版社の他の女性社員にも同じ手口で迫り、労働党への推薦を条件に性関係を強いていたのだった。
私は、出版社編集部の筆写工のポストから追いやられ、印刷工場の一労働者に格下げされた。ホワイトカラーからブルーカラーにされたのだ。こうして私の入党への思いは無理やり断ち切られた。
女性を諦めに追い込む男性中心の文化
私が地方の中学4年生だったころ。1学期の試験期間中に、革命史の教師A(既婚男性)が、学級の幹部を呼びつけて再試験を行った。成績がよくない科目の再試験を受けさせ、優等生にして学校の評価をあげようとする意図があったようだ。ちょうど停電中でろうそくの火が灯されていた。教師Aは、クラスメートの隣に座り、模範解答の書かれた用紙を広げて見せつつ、彼女のお尻を触った。
肝っ玉の大きかったクラスの女子生徒たちは、次の革命史の時間に、教師Aをジロジロ見て、曖昧な質問をして答えを笑い飛ばすことで抗議の意を示した。もちろん主導者は私だったが、そうでなかったとしても、クラスの班長だったので、全責任は私にあった。
教師Aの私を見る目が徐々に冷ややかなものへと変わり、その目つきは担任の女性教師にも向けられた。
やがて私は家族とともに平壌へと引っ越すことになった。受け取った転学証明書を、平壌の学校の行政副校長に提出したら「こんな不良学生はうちでは絶対に引き受けれられない」と言い出した。それもそのはず、革命史の教師が「学習面では最優等生だ」とした上で、私に対する罵詈雑言を書き綴っていたのだった。
中学校3年生のときには、革命史の教師B(独身男性)が、キャンプに行った先で、クラスの女子生徒全員のそばに横になって体を触る事件が起きた。教師は教職を解かれた。
「それは性暴力だった」
性暴力は、北朝鮮で成功を夢見る女性のほとんどが避けて通れないブラックホールだ。私は22歳で初級党書記から性暴力に遭ってから、10年以上に渡って悩み続けた。性暴力被害のことではなかった。生活と人間に対する理解が不足していたか、現実に対処する能力が弱かったため、初級党書記の人生に傷を残したのではないかと悩んでいたのだった。答えが見つからないまま、その忌々しい出来事は私の脳裏から消えていった。
それが韓国に来てから3年経ったころに、ふと思い出されたのだ。初級党書記の行為は性暴力だった。性暴力加害者は、適切な法的制裁を受けるのが正義だと知った瞬間、心が楽になった。それは、30年以上胸の奥で抱えていたくだらない道徳的な重荷とやらを完全に下ろした瞬間だった。
チェ・ジニ(元朝鮮作家同盟詩人)