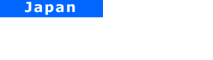韓国に入国した脱北者が2万人を超えてから久しい。少し関心を持って周囲を見渡せば、脱北者は私たちの周りに少なくない存在だ。
韓国社会で成功を収めた脱北者がたびたび紹介されるが少数に過ぎず、まだ多くの脱北者が北に残された家族を心配し経済的な困難と社会的な偏見に苦労している。
希望と期待を抱いて韓国にやって来たチョン・スンチョル氏を通じ、韓国社会の冷酷な一面を映し出している映画『茂山日記』は、日常で出会うことができる脱北者の姿を表現している。
パク・ジョンボム監督は、この映画でチョン・スンチョル氏を演じた。この映画のモデルとなった脱北者は胃がんで死亡した。
パク監督は「韓国社会への適応が難しい脱北者と疎外された人々に配慮し、彼らの生活に関心を持って欲しい」と述べた。
- 『茂山日記』を作るきっかけがあるとしたら?
チョン・スンチョル氏は私の大学の後輩だった。一緒に運動し酒を飲み3〜4年間を共に過ごした。実の弟と言えるほどだ。彼と知り合ってから貧しい暮らしを強いられている脱北者と沢山接するようになった。スンチョルや彼の友人らは幸せになるために韓国にやってきたが、韓国での生活は困難を極めた。就職も容易ではないようである。常に残念であると考えていた。
そんな中、スンチョル氏が胃癌でこの世を去った。その後、イ・チャンドン監督の映画の助監督をしているときに、スンチョル氏が私に送ったメッセージを見た。
「先輩、長編映画を見れずに先に行くけどすまない。きっと素晴らしい映画を作ると思います。僕らが作ろうとしていた映画を撮ってくれることを願います」との遺言が映画を作るきっかけとなった。
- チョン・スンチョル氏と過ごした事で、多くの脱北者と接点を持ったのでは。
スンチョル氏と共に過ごした事で脱北者が参加する『統一サッカー団』『一つの心サッカー団』の創立式も共に参加した。当時、KBSラジオが取材に来たが、私を脱北者だと思ってインタビューを要請された。それほど親密に付き合っていた。
彼らから脱北者の生活の多くの話を聞いた。酒を飲みながらブローカーから詐汲ノあった話や家族に送金した話などを聞き、就職が大変だと愚痴も聞いた。彼らは韓国での生活が余りにも大変な為、難民として英国や米国に行きたいと話していた。こんな話が映画の毎シーンに現れている。
- 出会った脱北者らが極貧生活を送っているというが。
私が出会った人々はマスコミに出てくる有名な脱北者ではなく、平凡な人々だった。協同農場にいた方々でこれといった技術も持っていない。内装工事や歯科衛生士など夢はあるが、資格の壁に阻まれていた。生活状況も良くなかった。今では全員が海外に移民していった。一人はシェフに昇進したという。
- 『茂山日記』が韓国社会に適応している脱北者の反感を買うのではないか。
延世大学には脱北者のサークルがあり、私がこの映画を撮ると言うと反感を表す方もいた。「脱北者に対する認識が良くないのに、何故この様な映画を撮るのか。私たちも懸命に生きようとしているのに、何故なのか」と言われた。
しかし、私は彼らが脱北者の全てでは無いが、苦労している脱北者と疎外された人々が映画の中と同じ様な経験しているということを公論化する必要があると考えた。スンチョル氏もそのような生活を送っていたので『義理』もあった。
- スンチョル氏はどんな人物だったのか?
陽気でいたずら好きで運動も好きな人物だった。夏休みにはボランティア活動もした。学校内の脱北者のサークルで会長をしていた経歴もある。
- 映画の中のチョン・スンチョル氏はかなり暗かったが。
脱北者はプライドが強い方が多い。生死の間を乗り越えて韓国に来たからかもしれない。自ら積極的な人生を生きる為に韓国にやってきたが、いざ韓国社会に定着すると誰もやりたがらない様な仕事しか出来ない。社会的な待遇も悪くなる。そして傷ついて苦しむ。この様な複合的な脱北者の心情をチョン・スンチョル氏を使って表現したものである。
-映画の国内外からの関心が高い。海外の映画祭での受賞歴も華やかだ。
この映画は過大評価されている部分がある。外国の映画祭関係者や記者は最後の分断国である朝鮮半島で、脱北者を題材にした映画である為に話題作りがしやすいからだろう。だから注目されたものであって、映画がこれほどまでに有名になった特別な理由はないと思う。
ヨーロッパ諸国は「多民族主義の失敗」や「移住労働者問題」などと結び付けてこの映画を見たようだ。ある国際映画祭で上映が終わると、白髪のある老人が僕に駆け寄り「これは私の話だ。とても良かった」と言ってくれるほど、共感を持ってもらえた。